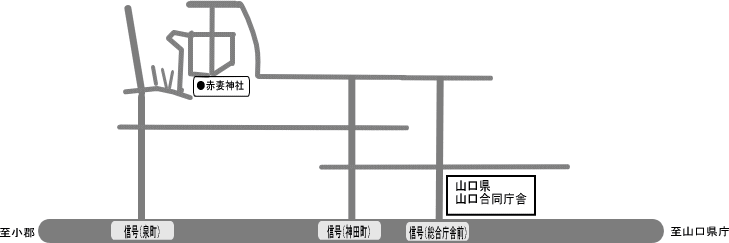錦小路頼徳は、文久三年(1863)八月の京都に於けるに政変によって都落ちし、長州藩に逃れて来た七卿の 当初、 三条公を始めとして有志の者は、錦小路頼徳は攘夷の先鋒となって赤間関の地へ来たのであるから、赤間関(下関)に埋葬すべきであると主張しました。しかし藩は、五卿の朝暮の参拝や藩主の弔祭に利便な為、山口での埋葬を望み、錦小路頼徳の遺体は山口に埋葬されることに決したのでした。そして三ヶ月後の七月三日に、藩主毛利敬親(たかちか)は三条実美卿とともに相計って赤妻山上に 頼徳の印二顆を御神体とした社殿を建て、錦小路頼徳卿の神霊を奉斎し、安加都麻神社と称したのでした。これが赤妻神社の創始でした。   錦小路頼徳卿墓所と祈念碑 右側=墓所 左側=社殿 やがて明治三年(1870)には三条公篆額の記念碑が墓のすぐ後方に建てられました。明治18年(1885)には官祭招魂社に列せられました。また昭和十五年(1940)には内務省令により、頼徳公の墓地を含んだ官祭招魂社を朝妻護国神社と改称したのでした。 大東亜戦争後の占領期である昭和二十二年(1947)には占領政策に配慮し、社号を赤妻神社と改称するにいたりました。 朝妻神社の戦後は、国家の維持管理を失い、もともと特定の崇敬社や多数の遺族を持たない特別な招魂社であったことから、山頂の社殿や境内は荒廃するに至りました。そこで昭和四十三年(1968)に明治維新百年記念にあたり社殿の復興整備が計画されましたが、実行はなりませんでした。 しかしその後、当地の宅地造成に伴い赤妻山は平地となり、境内地は朝妻山麓の墓所隣接地に替えられ、、近年その地に社殿が建立されました。
|