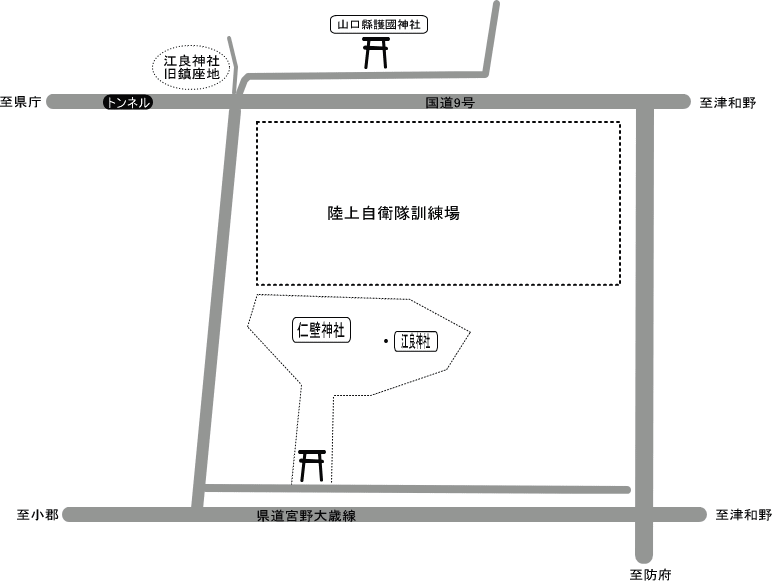四境戦争・戊辰戦争の戦死者九名を祀ったとされています。 四境戦争・戊辰戦争の戦死者九名を祀ったとされています。ところが当招魂社は藩庁所在地にあつために、恰も諸郡招魂場の総社のように扱われ、そして明治三年九月二十三日に防長最初の合同招魂祭が行なわれてからは、毎年この日(後に三月二三日)を祭日とし、江良神社と改称されたました。 しかし明治七年には江良招魂社と改められ、明治八年六月には官祭招魂社となりました。昭和十四年四月に護国神社制度が始められてからは江良護国神社と称せられました。  しかしながら昭和十六年に隣り合わせのような場所に一道府県に一社のみ許可される指定護国神社として山口縣護國神社が創建されたことで、それまでの江良招魂社の比重は軽くなったようです。そして昭和二十二年二月二十八日に占領軍施政に配慮して、江良神社と改称されました。 しかしながら昭和十六年に隣り合わせのような場所に一道府県に一社のみ許可される指定護国神社として山口縣護國神社が創建されたことで、それまでの江良招魂社の比重は軽くなったようです。そして昭和二十二年二月二十八日に占領軍施政に配慮して、江良神社と改称されました。現在では、毎年四月二十九日と十一月三日には神式の慰霊祭が山口縣護國神社で行なわれ、防長英霊塔では仏式の慰霊祭が行なわれていますが、考えて見れば近接して神仏の慰霊が行なわれるのも不思議な巡り合わせかと思います。  戦後は官祭招魂社としての国から保護も停止され、社殿の荒廃が進んだため、昭和三十年九月十三日に宮野地区の氏神である近くの仁壁神社境内に移され、境内社となって現在に至っています。 戦後は官祭招魂社としての国から保護も停止され、社殿の荒廃が進んだため、昭和三十年九月十三日に宮野地区の氏神である近くの仁壁神社境内に移され、境内社となって現在に至っています。[参照文献]
|