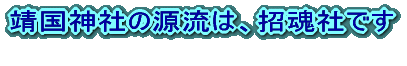
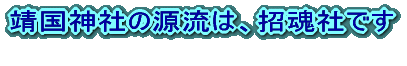
| 第六回 今回は 慶応三年に招魂場として開かれた地は、鳶ヶ巣という山の頂上であったことから参拝に不便なため、昭和十六年に「皇紀二六〇〇記念事業」として現在地に移転されました。   舟木護国神社(写真1) (写真1)の左奥に見える鳥居内の招魂碑群 上掲左の写真にある招魂碑は、鳶ヶ巣山の頂上の招魂場から移された招魂碑です。鳶ヶ巣山の頂上には、ささやかな拝殿が建てられていたようです。 〈・・・・この山を開くには舟木宰判管内の村々から毎日人を繰り出して勤労奉仕した。長藩自らの開設につき厚狭四本松毛利能登も来て三ツ星の幔幕を張りめぐらし工事を督励した。各村ではのぼり太鼓で先年の「殿様祝」の時のようなお祭り騒ぎでやって来た。各村から男女手拭頬かむり花笠を着け、テレンという浅いかごを持って三味線などもち出ししゃぎって出場した。四斗樽の鏡をぬいては酒は飲みほうだい、見物人は毎日大勢やってきた。 第一日の加勢は万倉である。ふごに鍬などを持って地味な身なりでやって来て開墾に従った。ところが第二日目は小野村であった。小野村では一同揃いの着物を着て幟に太鼓を打って余興気分でやって来た。次いで藤曲の者は船着き場であるので小舟をかついで見事な飾りつけをしてやって来た。それから各村毎日趣向をこらして余興気分で来るようになった。最初に来た万倉の者は不平を言い出した。「沙汰の仕様が悪い、万倉村の体面にかかる」というので終わりの日に余興気分で再度出場した。こんな風で開墾の方はあまり仕事がはかどらないので、最後には人を雇って開いたということである。・・・・・〉 こうした史話を知るとき、招魂場の開設が、現代から想像される慰霊といった厳粛な雰囲気で行われたのではなく、郷土の勇者の霊魂を祀る場所をつくるという、わいわいした雰囲気、祭りの雰囲気で行われた場合もあったことが想像され、なんとも純朴な幕末期の人々の心情が窺えるようで、ほっとする。 それに比べると、今日はなんと堅苦しく招魂場や護国神社を考えてしまっているように思われてならない。慰霊ということに偏重し過ぎていて、称えるということが少なすぎるのではないだろうか。自分が戦死したとして、慰められ、涙されるばかりでは、寂しい気がする。「良くやった」「立派だった」「犬死にじゃなかったぞ」「みんなの為に為ったぞ」と誉め称えられる方が、慰められる気がするが、皆さんはどう思われるでしょうか?
|