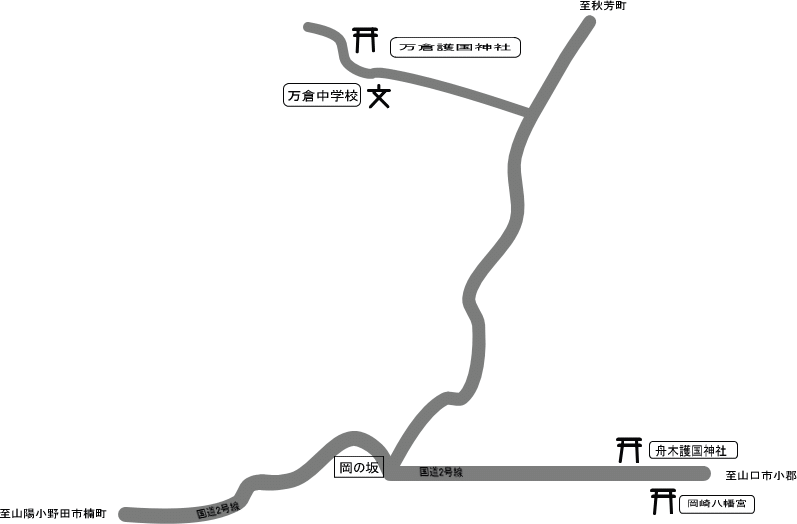万倉護国神社
万倉護国神社(旧称 峠招魂場)。峠招魂場は、慶応3年(1867)、万倉村主の国司健之助鈍行が、土井峠山に京師の変(禁門の変=1864年)の責を負って自刃させられた義父の国司信濃をはじめ、戦死した26名の霊を祀って開かれました。峠招魂場は、明治34年(1901)官祭招魂社となり万倉招魂社と称しました。地元では万倉村招魂社といっています。昭和14年指定外護国神社となり、万倉護国神社と称しました。
 
(国司信濃像と本殿裏の招魂碑群) (万倉護国神社)
現在、万倉護国神社は、宇部市(旧厚狭郡)楠町に鎮座していますが。現在の社地と社殿は、昭和17年に峠招魂場とは別の地に新たに造営された社殿です。峠招魂場には、近年まで招魂碑がありましたが、その招魂碑も、現在は万倉護国神社本殿裏の境内に移されています。
万倉護国神社の祭神の追祀の推移を紹介しておきます。
| 年代 戦役 |
祭神 |
累計 |
| 元治元年 禁門の変 |
19名 |
19 |
| 慶応二年 四境役 |
12名 |
31 |
| 明治二年 佐賀役 |
2名 |
33 |
| 明治十年 西南役 |
4名 |
37 |
| 明治二十七年 日清役 |
6名 |
43 |
| 明治三十三年 北清役 |
1名 |
44 |
| 明治三十七年 日露役 |
11名 |
55 |
| 大正七年 シベリヤ役 |
2名 |
57 |
| 昭和十年 満州匪賊討伐 |
2名 |
59 |
| 昭和十二年 日支事変 |
13名 |
72 |
| 昭和十六年 大東亜戦争 |
132名 |
204 |
祭神の追祀されていったこのような様子を見るとき、日本の一つの県である山口県の、それも厚狭郡万倉村という小さな村でありながら、そこからも近代日本の各戦役に漏れなく戦死者がでていることが分ります。
こうした環境にあった為か、万倉護国神社を造営する山の開拓は「この山林開拓には、万倉村民一切挙げて勤労奉仕、総て村当局の心配により、各種団体員男女問はず再三にわたり奉仕、山の三分の一程掘り下げり(河本忠澄記)」であった記されています。
現在も、崇敬者によって護持され、年々の祭祀も続けられています。
この万倉護国神社の拝殿左壁には、 「黄泉の武士」 という次のような詩が墨書されていて、春の大祭及び秋の墓前祭で参拝者全員、祭典の途中でこの詩を奉唱するということです。戦死した勇敢な戦士を称えるすばらしい詩だと思います。こうした招魂社祭祀の中に招魂社の本来の姿を見ることができるように思います。
黄泉の武士
あな勇ましの益良雄や 君がみ為に身を捨てて
戦に立つる旗のごと 御霊ぞ世々に仰がるる
あな勇ましの益良雄や
あな功しの武士や 国の御為に身を捨てて
戦にかざす太刀のごと 御霊ぞ世々に輝ける
あな勇ましの益良雄や

|